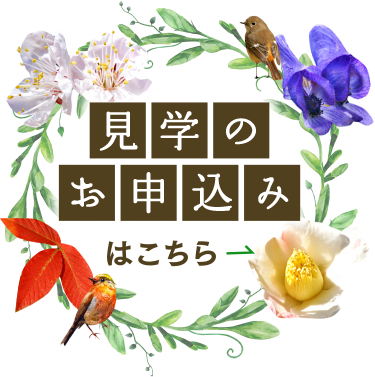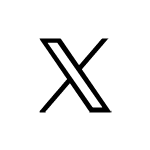バクチノキ

| 学名 | Laurocerasus zippeliana Browicz |
|---|---|
| 和名 | バクチノキ |
| 科目 | バラ科 |
| 見頃 | 10月頃 |
バクチノキについて
バクチノキは、関東地⽅以⻄の本州・四国・九州・沖縄・台湾に分布する常緑性の⾼⽊で、⾼さは10~20 mとなることもあります。葉は互⽣し、葉柄の上部には1対の蜜腺があります。
花期は秋で、葉腋に葉より短い総状花序を出し、⼩⽩花を多数咲かせます。円形の⼩さい花弁を5枚持ち、雄しべは30~50個あり花弁よりかなり⻑く、雌しべを1個持ちます。果実は卵形から楕円形、⻑さ1.5~2 cmで、翌年の春ごろに紫⿊⾊に熟します。バクチノキは、樹⽪が鱗⽚状に剥がれ落ち、その跡が紅⻩⾊のまだら模様になるのが特徴です。
バクチ葉について
新鮮葉を⽔蒸気蒸留しその留液をバクチ⽔として鎮咳・去痰を⽬的に⽤いられていました。葉には、⽣薬の杏仁(アンズの種⼦)と同じように⻘酸配糖体を多く含み、かつてはキョウニン⽔の製造原料としても⽤いられ、バクチノキから製造されたものはバクチ製キョウニン⽔と呼ばれていました。
また、⺠間的に、新鮮葉を細かく刻んで煎じて作られた煎液を「あせも」の患部に外⽤で⽤いられました。